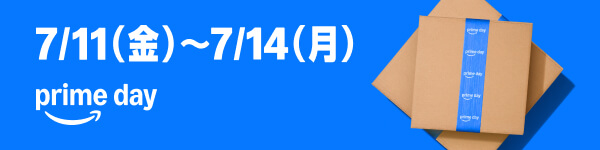明治の文豪・夏目漱石の「坊っちゃん」のあらすじと読書感想文です。
Google検索のトップに出てくる「坊っちゃんの読書感想文」があまりにもつまらなかったので、40年以上に渡って「坊っちゃん」を何度も読み返している私が、これぞ「坊っちゃんの読書感想文」というものを、書いてみました。
「坊っちゃん」の読書感想文だから、かなり毒舌です。
ご存知ですか?夏目漱石という人は恐るべき「毒舌家」で、なかでも「坊っちゃん」は、とんでもない毒舌のオンパレードなんですよ!
なお「坊っちゃん」は著作権が消滅した作品のため、著作権消滅作品を電子書籍で公開・提供している「青空文庫」で無料で読めます。

坊っちゃん
英訳バージョンもあります。

Botchan (English Edition)
夏目漱石『坊っちゃん』のあらすじ
「親譲(おやゆず)りの無鉄砲(むてっぽう)で小供(こども)の時から損ばかりしている」の書き出しで始まる物語。
無鉄砲な「おれ」は、母、父と相次いで死に別れ、兄からも疎まれる。
ただ一人「おれ」を慕って、世話を焼いてくれるのが「清」というばあさんの下女だ。
物理学校を出た「おれ」は、無鉄砲に四国の中学校への赴任を即決してしまい、停車場で清と涙の別れをする。
四国の中学校では「おれ」の活躍で、うらなりの婚約者をうばったり、芸者遊びをして朝帰りする「赤シャツ」こと教頭と、その腰ぎんちゃく「野だいこ」こと画学教師をこらしめ、ゲンコツをぽかぽかくらわし、天誅を加える。
東京に戻った「おれ」は街鉄の技手になり、清を呼び寄せるが、清はしばらくして肺炎で亡くなってしまう。
「おれ」は、
「後生だから清が死んだら、坊っちゃんのお寺へ埋めて下さい」
という清の願いを叶えてやる。

「坊っちゃん」読書感想文
「坊っちゃん」は、田舎者の試金石、あるいは、踏み絵だ。
主人公の「おれ」は、四国へ到着するやいなや、ウエストランド井口も、かつての有吉弘行やビートたけしも真っ青の毒舌を吐きまくる。人の様子や漁村のあり方、汽車のサイズにまで「マッチ箱のよう」と悪態をつく。
真っ裸に赤ふんどしの船頭を見て「野蛮な所だ」、大森くらいな漁村を見て「こんな所に我慢が出来るものか」、中学校の場所を「知らんがの」と云った小僧に「気の利かぬ田舎者だ」、宿屋で出迎えた女には「やな女が声を揃えて」・・・・。随所に「親譲りの無鉄砲」を散りばめているから、それを免罪符にして「おれ」は言いたい放題だ。
これに目くじらを立てるようでは、都会人とは言えまい。私のような西日本の片隅で生まれ育った人間にとっては、そこまで地方都市を馬鹿にするのもいかがなものだろうかと言いたくなる。
全く同じことを、現在のSNSなどで有名人がつぶやけば、たちまち大炎上。フワちゃんどころの騒ぎではなくなるだろう。
田舎育ちの私は、「おれ」が四国に来て毒舌をこれでもかと吐きまくる場面で、自分に言い聞かせるのだ。「無鉄砲だから、彼は無鉄砲だからなのだ」と。
令和の今が厳しすぎるのか、明治という時代が「ひどい」のか、意見が分かれるところだと思うが、最終的に「文豪」として歴史に名を残した漱石の言う事だから、「おれ」の毒舌に怒っちゃいけないんだろう。・・・にしても、最後には「この不浄な地」とまで「おれ」に言われている。
作者もいきなり毒舌を吐くのはさすがに悪いと思ったのだろう。その前に「おれ」がいかに無鉄砲で、粗雑で、乱暴者かが語られ、家族からも疎まれていたかという前置きがある。
なんなら、先に毒舌の部分を書いて、これじゃさすがに田舎者が怒るかもしらんと思った作者が、前の部分の「無鉄砲エピソード」を書き足したんじゃなかろうか、とすら思う。
しかし、毒舌の連続は読んでいて小気味いい。まだ記憶に新しい、ウエストランドのM-1のネタや、昭和を席巻したツービートの毒舌漫才が大爆笑をとったり、中には腹を立てていた人もいたはずなのに、反論を許さなかったように、田舎だの野蛮だのと畳み掛けられても、いつしか笑ってしまっている自分がいる。
毒舌が小気味いいのは当たり前で、誰もが心の中で少しは思っているものの、口に出すのははばかれる悪口を、代弁してくれているのだから、ありがたいのだ。心の中にできた心のゴミ屋敷のゴミを、かわりにポイポイ捨ててくれるようなもので、他人の代弁なのにデトックスした気になれる。
漱石の上手さは、一言二言の田舎批判なら反感を買うだろうことを、ぐうの音も出ないほどに悪く言うものだから、一周回って「私も実はねえ・・・田舎ってやだな・・・なんて思ってたんですよね」と、私のような田舎者まで共感してしまう。
映画「翔んで埼玉」が、埼玉をあれほどディスっているのに、埼玉で大ヒットした現象と同じことが、すでに明治時代に起こっていたのだ。だから愛媛松山は今でも「『坊っちゃん』の舞台」「『坊っちゃん』のモデル」と大々的にアピールし、温泉や電車やあらゆる名物に「坊っちゃん」の名を冠している。
「こんな所に住んでご城下だなどと威張っている人間は可哀想なものだ」
作中で作者に、そこまで言われしまっているのに!だ。
反面、作者は幼い頃に里子に出されたり、母親と死に別れたりして、家族愛や親子愛というものと無縁だった。その事と一緒くたにしてはいけないのだろうが、やはり主人公の「おれ」がここまで毒舌家で、粗雑で乱暴なのは、どこか孤独で、誰からも愛されなかった作者自身を投影しているようにも感じた。
なぜなら、私も幼い頃に相次いで父、母を亡くし、親戚をたらい回しにされたから、よくわかるのである。
生後すぐ里子に出されたり、実家に連れ戻されたり、また養子に出されたりという漱石の辛く悲しい幼少期には、様々な事情があったのだと思うが、それを一言「無鉄砲」という言葉に集約して、無鉄砲ゆえに父も、母も、兄も自分を嫌っていたと表現しているあたり、漱石の孤独や悲しみを感じる。
そして、ただ一人の「おれ」の理解者である下女の「清」。この人だけは作者の「創作」に違いないと私は思う。孤独な幼少期を送った私だからよくわかるが、実際には清のような、神様のような「救い」の存在はいないのである。多くの大人は親の無い子を持て余し、敬遠し、遠ざけようとする。
漱石もそうだったに違いないと、私は確信している。
この物語は読めば読むほど、漱石が「自分にも清のような存在があれば、まだ人生が救われたのに」という願望を詰め込んだ物語、と思えてくる。
だから、清だけはベタベタに「おれ」を可愛がる。理想の下女であり、理想の「たったひとりの理解者」なのだ。現実には、そんな人は存在しない。清は甘いものや、夜食を隠れて渡し、3円の小遣いまでくれる。さらに、「おれ」が四国に赴任する時は、目に涙をいっぱいためて、いつまでも汽車を見送っている。
清のモデルは、漱石の親友 米山保三郎の祖母・清といわれているが、これはあくまでもキャラクターの土台となった人だと私は思う。物語の中で「自分をただ一人、溺愛してくれた存在」として清を描いたのは、漱石の切ない夢、願望、こうだったらなあ・・・という妄想だ。そんな人は、きっと存在していなかった。
だから最後に「清」は亡くなっている。作り上げたキャラクターなので、物語といっしょに「清」も葬られているのだ。
NHKで数年前「夏目漱石の妻」というドラマを観た。漱石は「そこまで?」と驚くほどに常にイライラし、怒鳴り散らし、暴れまわり、妻を苦しめる。でなければ神経衰弱で暗く落ち込んでいる。そんな夫に振り回された妻の鏡子は、ついに自殺未遂までしている。
ドラマだから当然、多少のデフォルメはあるだろうが、漱石の妻・鏡子が川に身を投げて投身自殺を図ったりしたことは事実だから、漱石から妻への罵詈雑言や癇癪、暴力までふるったというのも本当の話だ。
「清というのは妻・鏡子の本名がキヨだから、『坊っちゃん』は漱石から鏡子に宛てたラブレター」
という説もあるにはあるが、私は漱石にもし「清」のような存在がいたら、あそこまで神経衰弱やノイローゼの症状が起きなかったのではないかと思う。
私は、漱石はどこまでも、「俺は誰にも愛されない」という呪縛にとらわれていた「自己憐憫」の塊のような人のゆえに、毒舌を吐き、妻を罵り、暴力をふるい、四九歳という短い生涯を終えた・・・と思っている。
胃弱や胃潰瘍、痔瘻、リウマチ、漱石の作家活動の後半は病気のオンパレードだ。
ただでさえ三九歳から四九歳という短い作家活動の中で、実質的に健康(小康状態だか)だったのはわずか五年間だ。
いっそ他の作品でも、「坊っちゃん」のように、毒舌を並べ立てれば良かったのに。
反省したのか、落ち込んだのか「こゝろ」のような、しおらしい物語を書いてしまったから、漱石は四九歳で世を去った。返す返すも残念なことだ。五〇代六〇代の漱石が、どんな物語を生み出したか、知りたかったものである。
「坊っちゃん」で作者が言いたかったこととは
のちに夏目漱石は、文部省から「文学博士の学位を授与する」と一方的に通達されて激怒し、博士号を拒否するという「事件」を起こす。このことから漱石には「反権力主義」「反権威主義」のレッテルが貼られる。
国費でイギリスに留学したくらいだらから、「反権力主義」もないだろう。だったら留学費は自腹で行くべきでは?とも思うが、少なからず漱石という人には「反骨精神」のようなものがあって、何であれ人から強要されたり、押し付けられたりするのが大嫌いだったことがわかる。
博士号辞退事件で漱石は、
「ただの夏目なにがしで暮らしたい希望を持っております」
と文部省へ返信する。
そんな人だから、実際に漱石が四国へ教師として赴任した時なども、田舎の中学の校長の偉そうな態度など、たまらなく嫌悪感を抱いただろう。
「偉そうにするやつが、とにかくおれは嫌いなんだ」
ということは、この物語の一番のテーマかもしれない。
さらに、「田舎の人」がとにか作者は嫌い。「おれ」が入った蕎麦屋を「滅法きたない」と表現する場面があるけど、ただ汚いと言っているのではなく「東京を知らないのか、金がないのか、滅法きたない」と言っている。つまり逆に考えれば、東京は皆、金があって、どこもきれいな街なんでしょう。
世の中には「坊っちゃん」を読んで、
「何が名作だ、胸糞悪い」
と言っている人もいる。自分の正義感を押し付ける坊っちゃんに対して、
「不快でした」
という意見もあった。
私も、これだけ毒舌を吐かれて、愛媛松山の人はもう少し、怒ってもいいのに・・・・と思う。
最初に「田舎者の試金石、あるいは、踏み絵」と言ったように、これに目くじらを立てて批判したり、腹を立てたら「田舎者」あるいは「無粋」「堅物」「冗談の通じない人」と言われそうだ。毒舌漫才に本気で怒ったら、
「そんなことに怒るなんて、人間が小さい」
と言われそうだから、面白いと笑う。盛大に評価する。自分の寛容さを示すためにも、笑って済ませる。
何かそんな戦いを「都会人」で「江戸っ子」で「東京生まれ」の漱石から、挑まれているような気がするのが「坊っちゃん」だ。
「この物語に腹を立てておられるのですか?余は田舎者に生れなくって、まあ善かったと思う」
漱石なら、そんなふうに言うのではないか。
とにかく粋で洒脱が大好きな江戸っ子の漱石だから、高等遊民が理想の人物像なら「田舎者」はおそらくその対局にいる、漱石が最も、誰よりも、嫌う存在なのだろう。
坊っちゃん湯、坊っちゃん電車、坊っちゃん団子。なんにでも「坊っちゃん」をつけて自虐がすぎる。松山の人は、本当にもう少し、怒ったほうがいい。